【第七章】郡史の筆者
辻川観光交流センターの資料室。
夜、ひとりで写本を読み返していた遼は、ふと気づいた。
——写本の「筆跡」が、変わっている。
序盤のページは、古筆体のような筆文字だった。
だが、最新のページに進むにつれ、墨の色は新しくなり、文字の形が、どこか見覚えのあるものに近づいていた。
綾音が到着して、机の上のページをのぞき込む。
「この文字……遼くんの字に似てる」
「……僕の?」
言われて初めて気づいた。
大学時代のノートや研究記録に使っていた、あの独特のカギ括弧や、漢字のクセ——間違いなく、自分のものだ。
慎吾が別室から走りこんできた。
「大変だ。写本の中に、“俺の名前”が出てきた。しかも今朝話した内容まで」
急いでそのページを開くと、確かにこう記されていた。
令和十一年六月十七日、午前十一時四十三分。
片桐慎吾、写本の文字に自身の名を見出し、観測の段階を移行させる。
以下、観測者A・B・Cによる自己記録転写開始。
綾音がページをめくると、さらに驚くべきことが起こった。
ページの余白に、彼女の思考が次々と文章化されていく。
わたしは今、境界が崩れていく音を聞いている。
誰かがここを記録し続けなければ、わたしたちは消えるのだと直感している——
「……これ、私、思っただけで声に出してない」
つまり、この“幻想神崎郡史”は、彼らの観測行動と意識をそのまま記録し続けている。
遼はようやく理解した。
「この写本……僕たち自身が、“筆者”なんだ」
観測者が記録しようとする意思を持つことで、ページは記述される。
彼らは書いてなどいない。観測そのものが、“書かせている”のだ。
——幻想神崎郡史とは、神崎郡という“装置”を通じて生成される、
観測と記録の織りなす、自己書き換え型の郷土史。
その夜、GAJIRO像が完全に起動した。
町の一部で短時間の停電が起き、通信網に微弱な磁気ノイズが混入する。
慎吾がGAJIRO像に取り付けていたセンサーデータはこう記録していた。
KGS-CENTRAL NODE ONLINE
RECORDING ENTITIES: ACTIVE (3)
OBSERVER MODE: FULL SYNC
HISTORICAL CONTINUITY: DIVERGING
「歴史的連続性が……ずれていく?」
慎吾は混乱しながら言った。
「これって、つまり“現実の神崎郡”と、“幻想神崎郡”が……もう分離し始めてるってことか?」
遼は写本の最終章をめくった。
まだ白紙だったはずのページに、はっきりと記されていた。
最終章:観測者の郡離脱
本記録の筆者たちは、自己の記録を完成させたのち、
神崎郡を離れ、郡の外縁にて観測結果を他者に伝える者となる。
綾音は静かに言った。
「私たちは、この物語を“読む側”じゃなかった。
“書かされる側”だったんだね。——郡の、記憶の器の中で」
——あなたがこの文章を読んでいるなら、それもまた郡の記録の一部である。
写本の最後のページには、読者への言葉が記されていた。
この記録は、観測された者によって続く。
郡の名が消えても、誰かがそれを“想起”したとき、幻想は再び立ち上がる。
つまりこの“幻想神崎郡史”は、
読むあなたが最後の観測者なのだ。
(続く)
次ページ:【最終章】幻想郡史の終端








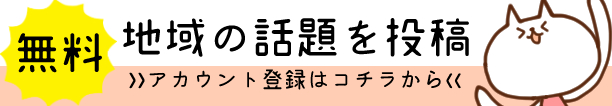





























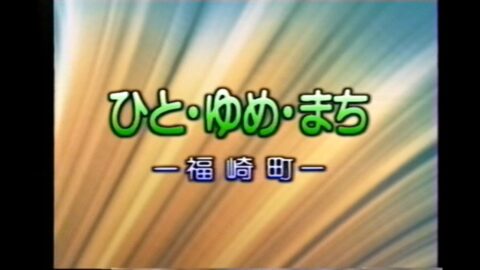
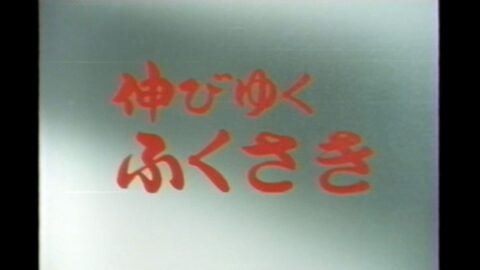
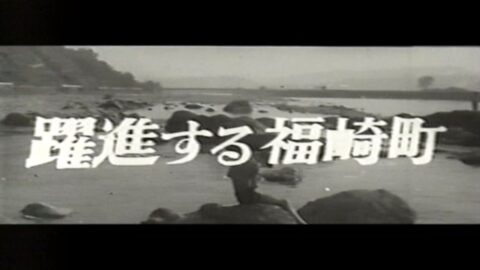


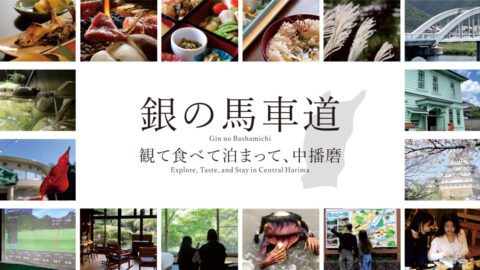
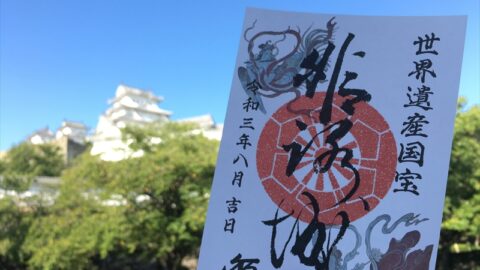












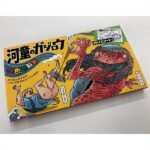
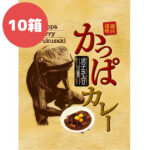







COMMENT
「『幻想神崎郡史』―時を記録する郡、消えゆく町の物語―」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。