【第四章】郷土と幻想の境界
GAJIRO像が動いた。
それは、誰かのいたずらや思い込みではなかった。
片桐慎吾が設置した独自のセンサーカメラが、それを“記録”していた。
夜明け前の辻川山公園。
普段なら誰一人いないはずの時間帯に、GAJIRO像の足元から、微細な振動と弱い磁場の変化が検出された。
「ただのマグネタイトじゃ説明がつかない……この像、何で作られてるんだ?」
慎吾の言葉に、遼は首を振った。
「表層はFRPだけど、内部に“共振核”のようなものがあるはずだ。……この像自体が、“記憶の収束点”なんだよ」
遼と綾音は、郡内の他の伝承スポットにも向かった。
市川町の“天乙女の水”——旱魃でも涸れない湧水。
神河町の“鬼の足跡”——岩盤に残された巨大な足型。
福崎町の“妖怪ベンチ”シリーズ——動くはずのない像が、人の気配に反応する。
綾音は呟いた。
「全部つながってる気がする。“見えない記録装置”としての郡……妖怪たちは、その表現装置なんじゃないかな」
——妖怪は、郷土に生きる記憶の擬人化である。
それは文学的な比喩ではなく、実体を持った現象だった。
遼はノートにメモした。
妖怪=観測された郷土記憶の端末
→ 郡内に複数存在。各端末は地域の暮らしと密接に接続
→ 出現条件:磁場変動・記録再生要求・住民の記憶刺激
写本には、また新たな行が浮かび上がった。
神崎郡に記録された記憶は、象徴と形態を伴い浮上する。
妖怪伝承、風習、地名、祠。すべては記憶再生装置の一部。
境界が薄くなるとき、“幻想”と“現実”は交差する。
四月上旬。福崎町・辻川界隈。
夜、人々が妙な夢を見るようになった。
夢の中でGAJIROが話しかけてくる。
「ここを覚えていてくれるか」「郡のことを忘れないか」と。
それは恐怖ではなく、どこか懐かしい感覚だったと、多くの町民が語った。
遼たちは、その日からのGAJIRO像の振動ログを解析する。
結果は驚くべきものだった。
夢が語られた夜と、像の振動発生時刻が一致していた。
慎吾がつぶやいた。
「まさか、像が“郡の意識”とリンクして……住民の夢にアクセスしてる?」
綾音は否定しなかった。
「郡って、町じゃなくて、意識かもしれない。……一つの巨大な“記憶人格”」
——土地には記憶がある。
それが限界に達したとき、人格化し、語りかけてくる。
その語りの形式が“妖怪”であり、“伝説”だった。
郡内の小中学校でも、変化は始まっていた。
「黒板に勝手に文字が浮かんだ」
「だれもいない図書室で、郷土資料が開いていた」
「祖父母の名前を知らないはずの同級生が、いきなり口にした」
不可解な出来事が、記録される。
そして、写本には次の一文。
境界はほぼ消失。郡の記憶は住民に直接アクセスを開始。
幻想と現実の分離が困難になる。以後の記録は“相互作用”に依存。
綾音が顔を上げて言った。
「このままだと、現実の“郡”のほうが飲み込まれてしまう。幻想に」
遼が頷く。
「だからこそ、僕たちが“記録者”として踏みとどまらないといけない。郡を飲み込むんじゃなく、“書き出す”んだ」
写本の役割は、幻想が現実を侵食する前に、“記録”として固定すること。
それは、終わりの前に行う最後の“観測”なのだ。
GAJIRO像の目が、どこか遠くを見つめているようだった。
(続く)
次ページ:【第五章】人口ゼロの村の記憶







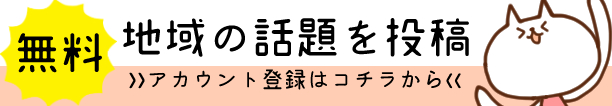





























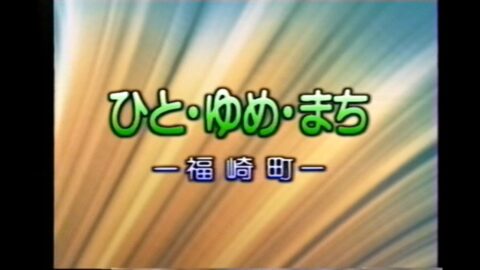
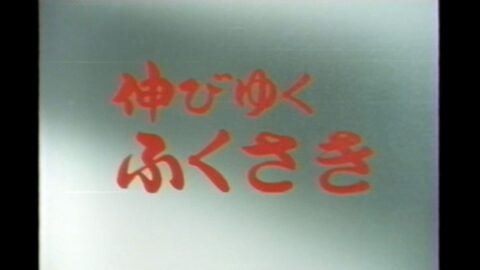
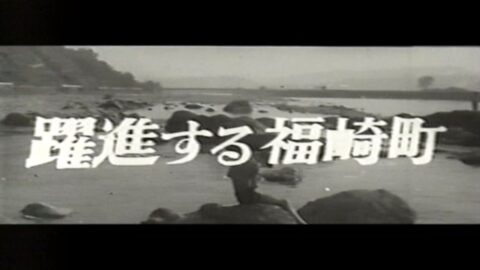


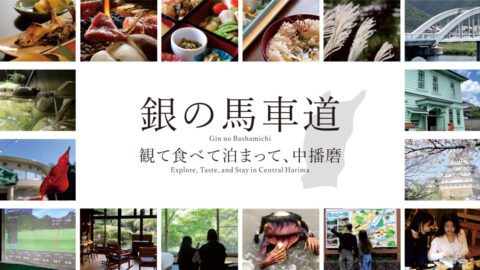
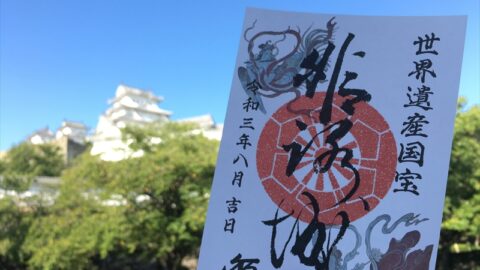












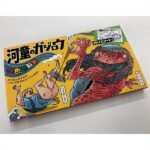
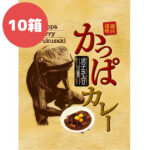







COMMENT
「『幻想神崎郡史』―時を記録する郡、消えゆく町の物語―」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。