【第一章】郡に響く声
2029年、早春。福崎町にある天野遼の自宅には、毎日のように郷土資料が届けられていた。
彼は町の観光文化財課の外部研究員として、「神崎郡史」の再編に取り組んでいた。新しい郡の歴史を編むという、大きな役割。だが、その作業の途中で遼は、ひとつの違和感に突き当たる。
——写本の文が、昨日と違っている。
「2030年、郡の境界が消え、地の記憶は失われるだろう」
数日前にはなかったその一文は、くっきりと墨で記されていた。
紙質も字体もまったく同じ。だが、確かに書き加えられていた。
「まさか、誰かが書き足した?」
そう考えてページをめくっていくと、さらに奇妙な箇所があった。
「この写本は、筆者アマノによる、未来からの記録である」
——アマノ? 自分の名前と同じ?
冗談では済まされなかった。神崎郡史の原本は明治期の写本で、町立図書館の地下金庫に保管されており、出入りは厳重に管理されている。研究用に与えられた複写は、遼しか触っていない。
さらに不審なことが続く。
市川町の旧村から、無人であるはずの空家に“灯りがついた”という連絡。
神河町の古い神社で、封印された「記憶杭」がずれていたという報告。
そして何より、GAJIROの像が、首を20度右に向けていたという目撃情報。
「地面が動いた? 地震のせい?」
町役場の広報担当・片桐慎吾は、冗談混じりにそう言った。だが、その目には、明らかな警戒の色があった。
遼は、自らの研究室に戻ると、机の上に広げていた神崎郡の古地図と、現代の地図を重ねて見比べた。
不思議なことに、ある地点だけ、どちらの地図にも「地名が書かれていない」。
——存在しない土地。だが、両方に「空白」として存在している。
そこには、地図ではただの森が広がっているが、かつて廃村になったという「北山集落」があった。
その晩。
遼のもとに一本の電話が入る。
「天野先生、北山で人影を見たと通報がありました。明かりも……誰も住んでないはずなのに……」
受話器の向こうで、郡の“記憶”が囁いていた。
その声を聞いたとき、遼は直感した。
——神崎郡が“何かを思い出そう”としている。
それが「消滅」を前にした、最後の叫びなのか、あるいは——
次なる歴史の“扉”を開く音なのかは、まだ分からなかった。
(続く)
次ページ:【第二章】写本の予言

















































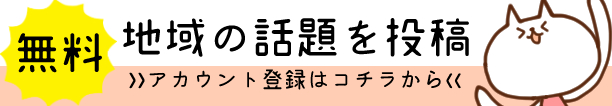




COMMENT
「『幻想神崎郡史』―時を記録する郡、消えゆく町の物語―」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。