【第五章】人口ゼロの村の記憶
神河町の役場から、古びたファイルが慎吾のもとに送られてきた。
表紙に書かれた名前は「和之原(わのはら)」。
かつて炭焼きと紙漉きで知られた、小さな山村。昭和55年(1980年)、正式に「無人化」が確認された集落だった。
慎吾は言った。
「この村、郡内でも数少ない“完全消滅集落”なんだよ。今はもう、地図からも消えてる」
遼と綾音は、すぐに現地へと向かった。
車道は途中で途切れ、あとは徒歩で尾根を越えるしかない。木の根に足を取られながら、二人は静かな山道を登っていく。
まるで空間が、こちらの侵入を拒んでいるようだった。
30分ほど進むと、ふいに風が止んだ。
音が消え、温度が下がる。
二人は目を見交わした。——これまでと同じ、記録が再生される前兆だった。
突然、木々の間に空が開け、視界が広がる。
目の前に、村があった。
草木に埋もれながらも、瓦屋根の母屋、井戸、炭焼き窯、炭俵を積んだ荷車——すべてが、動かずそこにあった。
だが音がした。
水をくむ音、紙をすく音、子どもの笑い声。
「……いる?」
綾音が呟く。
「いや、“いた”んだ。これも再生記録だ。でも、今回は質が違う」
遼は感じ取っていた。
これまでの集落の記録には、どこか夢のような輪郭のあいまいさがあった。
だが、今この「和之原」は、記録というより、“実在”に限りなく近い。
ふいに、一人の老婆がこちらに振り返った。
白い手ぬぐい、腰に手を当てて笑う。
「まぁ、よう来なさった。火ぃ焚いてるで」
遼は一歩も動けなかった。
「記録が……記録のままじゃない。僕たちを“受け入れている”……?」
そのとき、風が再び吹き、老婆は薄れていくように消えた。
そして、空の色が変わり、まるで録画映像を早送りするように、村がゆっくりと朽ち始めた。
母屋の壁が落ち、屋根が崩れ、井戸が埋まり、やがて草がすべてを覆った。
最初に見た村の姿が、今度は「現実の時間」で再現された。
そこには、なにもなかった。
福崎に戻った遼たちは、写本を開いた。
和之原の記述は、既に記されていた。
和之原:記録完了。
人口ゼロ。記憶密度、高。
他者の意識干渉を受けず、純粋な郡記録として保持される。
記録は閲覧者の意識と同期し、一時的に再構成される。
「つまり……私たちが“ここにかつて人がいた”と信じた瞬間に、郡の記憶がそれを再現したってこと?」
綾音の声は震えていた。
遼は静かにうなずいた。
「誰も覚えていなかったからこそ、純粋なままで残っていた……人がいなくなった土地こそ、最も強く“保存”される」
慎吾が資料を持ってきた。
「これ見てみろ。“人口ゼロの地”は、郡内で今、五つある。
しかもその多くが、昭和50〜60年代に集団移転で消えた集落。……記録密度、異常に高いってよ」
GAJIRO像の目が、どこか暗いものを湛えていた。
その台座に、新たな彫刻が刻まれていた。
KGS.004-SUBNODE/0
「“サブノード”?……記録装置としての支点が、複数存在するってことか」
GAJIROは郡の“意識装置”。
失われた村々は“記録ノード”。
そして郡そのものが、巨大な地理情報体(ジオメモリ)だった。
その夜、綾音は夢を見た。
和之原の老婆が、再び現れた。
彼女は、夜の山道を歩きながら、振り返らずに言った。
「うちのこと、覚えとってな。名前、残してな」
その言葉の余韻が、朝まで綾音の胸に残った。
郡の記憶は、消えることなく、静かに語りかけていた。
(続く)
次ページ:【第六章】神崎断層と巨大装置








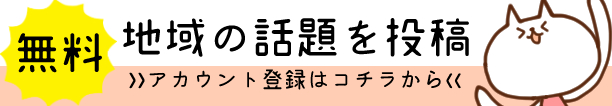





























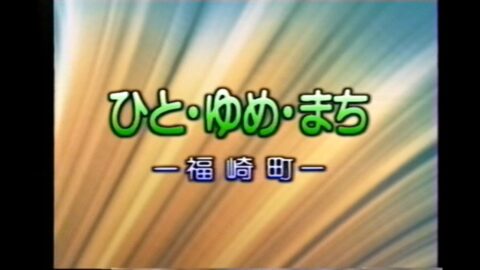
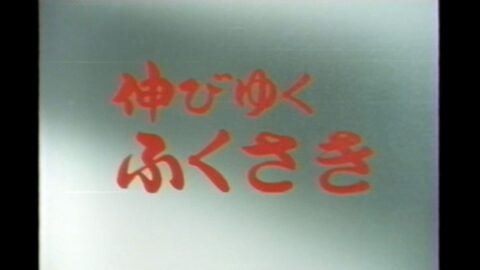
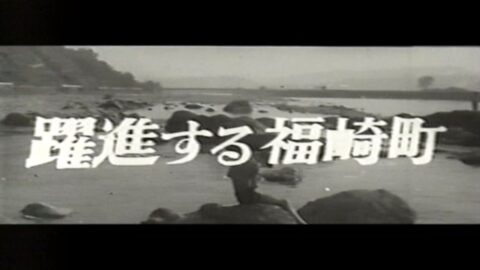


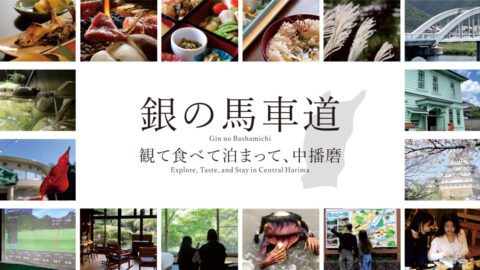
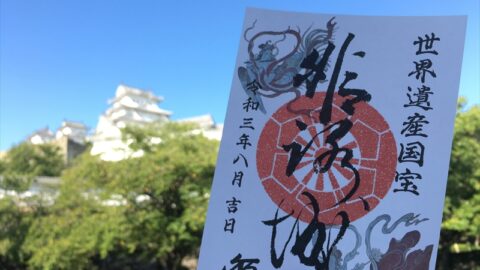












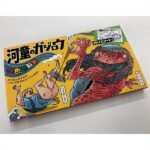
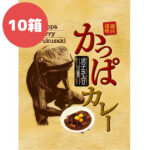







COMMENT
「『幻想神崎郡史』―時を記録する郡、消えゆく町の物語―」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。